ビジネス書や実用書など、仕事や技術の向上に役立つ本は、一冊1500円から2000円ほどで手に入れることが出来ます。
この、1500円ほどの額は安いのか、高いのか?それぞれ感じ方は異なるでしょう。
以前、ブログに載せましたが、本を読むことは筆者の話を聞くこと同じような効果があります。
本を読むことは筆者の話を目の前で聞くということ。その本が読み切れるかどうかは筆者のことを知っているかどうかか関係してくる。
たとえとして、読書は筆者との対話だと前提して、本を読む準備をしようという内容でした。
ここから、さらに一歩進んで考えてみると・・・読書はセミナーと本質的には同じで、読書はセミナーそのものと言っても良いのかもしれません。
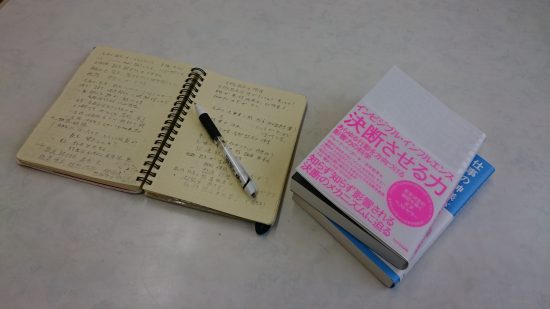
筆者の考え方を読んで知るのか?聞いて知るのか?
読書をして得られる知識・技術は、その本の筆者が知っていること・持つ技術です。
筆者が手にしているエッセンスを読んで、自分のものにすることが出来るという、最良の教材です。
本を読むことで得られる知識技術をもって、いま自分が始めたいことを推し進めたり、抱えている問題を解決することができます。
これは本で、文字を読んで行いますが、筆者のエッセンスを取り入れるという意味からすれば、筆者が行うセミナーに参加するのも同じことでしょう。
本にしても、セミナーにしても、筆者(講演者)が、不特定多数を相手に自分の持つ情報を読者やセミナー参加者に伝えるという意味で、いずれも同じように見えます。
要するに、読んで知るのか?聞いて知るのか?ということです。
ビジネス書や実用書は、一般的には1500円から2000円程度の金額層が多いですが、読書がセミナーと同じだと考えれば、この金額は恐ろしく安いです。
仮に、本の筆者のセミナーに参加するとして、セミナー料金は何千円から何十万円まで幅は広いですが、基本的に本を買うような値段では受けられません。
だとすれば、読書は紙上のセミナー。こんなに安い教材はないですよね。
ただし、読書もセミナーも、知識・技術という側面だけを見ると同じですが、受講形態は明らかに違うので、それなりに使うパワーが異なります。
私はこれを、自力と他力で考えてみました。
読書でセミナーと同じ効果を出すためには、自力と他力のコントロールが必要
読書は自分でその本を読み、時にメモをして、時に考え、自分に落とし込み、読み終えたら、その読書の効果を出すために自分で行動を起こしたり、なにか別の学びを開始したりします。
基本的に、読書からのアプローチでは、すべて自分でどうにかしなくてはいけません。自分でスタートし、自分で動かないといけません。
一方、セミナーに参加した場合は、とにかくセミナー会場に行けばセミナーが始まって、講師が話し出します。そこでしっかり聞くことは必要ですが、とりあえず座って聞いていれば、話がどんどん展開していくので、自分の意思が介入する部分は少ないです。(寝るのは別として)
そして、セミナーでは話してくれる相手の話を聞くので、ライブの熱を感じ、その情報を取り入れようという意欲が増しますし、一緒に聞いて学んでいる参加者がいることで、自分のほかにも学んでいる仲間がいるという仲間意識も生まれて(場合によっては学びのコミュニティーを作ったりして本当に仲間となる)、セミナーで受けた知識・技術をもって、次に自分で効果を出すための行動への意欲も躍進力も期待できます。
学ぶことは読書・セミナー、いずれも同じでも、学び方と学んだあとの行動力が違ってくると思うわけです。
これを分かりやすく説明するなら、「自力」と「他力」の概念をイメージすると良いかもしれません。
読書で情報を得て、その情報を元に自分で行動を起こそうとするには、本をしっかり読み、理解して考えて、自分に落とし込み、自らの意思をもって自分で動かなければなりません。基本的に、読書でアクションを起こすには、自力9割他力1割くらいかもしれません。
地力は自分の力。他力は外的要因による力です。
仮に、その本に、なんらかのウェブフォローがあったりすれば、若干力関係が変わってくるかもしれませんが、原則として読書は自力に頼らざるをえないのです。
他方、セミナー参加は言うまでもなく、講師の話とライブの熱があり、また質疑応答もあればその都度疑問点も解消できるし、仲間も作れるかもしれません。セミナー参加は外的要因が強いので、他力に寄りかかることができます。
セミナー参加では、そのセミナーの度合いにもよりますが、自力5割他力5割は保持できるかもしれません。セミナーのフォローによっては6:4とか、7:3もあり得るかもしれません。
しかしながら、セミナーでも、最終的に学んだ知識や得た技術を使って次のアクションを起こさないのであれば、9:1でも意味がないのですが・・・。
読書・セミナーいずれにしても、内容が同じとするならば、自分への負荷に耐え抜いていけるなら1:9でも身につくし、セミナーで9:1でも自分の力を全く出さないのであれば、それでもムダになりますからね。
自力他力の割合はあるとしても、自力でやることをやるのであれば、読書でも十分価値はあるということです。
読書が読書で終わる理由
よく、「ビジネス書をたくさん読んでいるけれど、何も変わらないよ」という話がありますが、そのパターンの多くは自力他力が1:9の読書だから、本を読んで満足して終わってしまうのでしょう。これが、読書が読書で終わる・読んだだけでなにも起きないということです。
読書は読書のその先が実は重要なんでしょうね。
読書だけで終わって、次の一歩を自力で自分だけで突き進むのが簡単ではないから、本と同じ内容のセミナーでも売れるわけです。セミナーに参加すれば、覚悟も参加のフィーも多額に支払っていて、自分を相当の高みに上げて臨むので、その時点で自力割合も高まっていきます。もちろん、他力に頼る部分も期待できます。
また、これもよく言われることで、「本に書いてあることを全部やったら成功する」という話・・・。
確かにそうなんだけれども、みんな出来ないから成功しないし、本は売れ続けるんですよね。
本とセミナーの内容がまったく同じで差がない場合には、本でも十分セミナーに匹敵する。
ただ、自分の覚悟が必要です。
相変わらずいつも、本は読んでいます。それに加えて、特にこのところセミナー参加が集中したことで、読書への意識も変わってきたように感じています。
自分なりに考えて、読書をセミナー受講のように出来ているときがあり、常にそうあれば読書の効果は期待できる!と、実感したことから、今日の記事につながりました。
読書はある程度時間がかかるもの。効果が分かっているなら意味のある読書にしたいです。
編集後記
年明け早々から、本を何冊も買い込んでいます・・・!
特に今週あたまから、学習欲が出てるので、こういう状態のときはここぞとインプットですね。まぁ、急に終息したりするのですが(笑)
昨日の夜は、先日行った租税教室の反省を活かして、来週の火曜日に再びやるときのためにネタのすり直しをしました。一気にやってしまおうということで、帰って風呂入って、深夜に一時間集中して書き込みしてました。
おそらく、これでだいたいOKなはず!